資金調達
カード選び
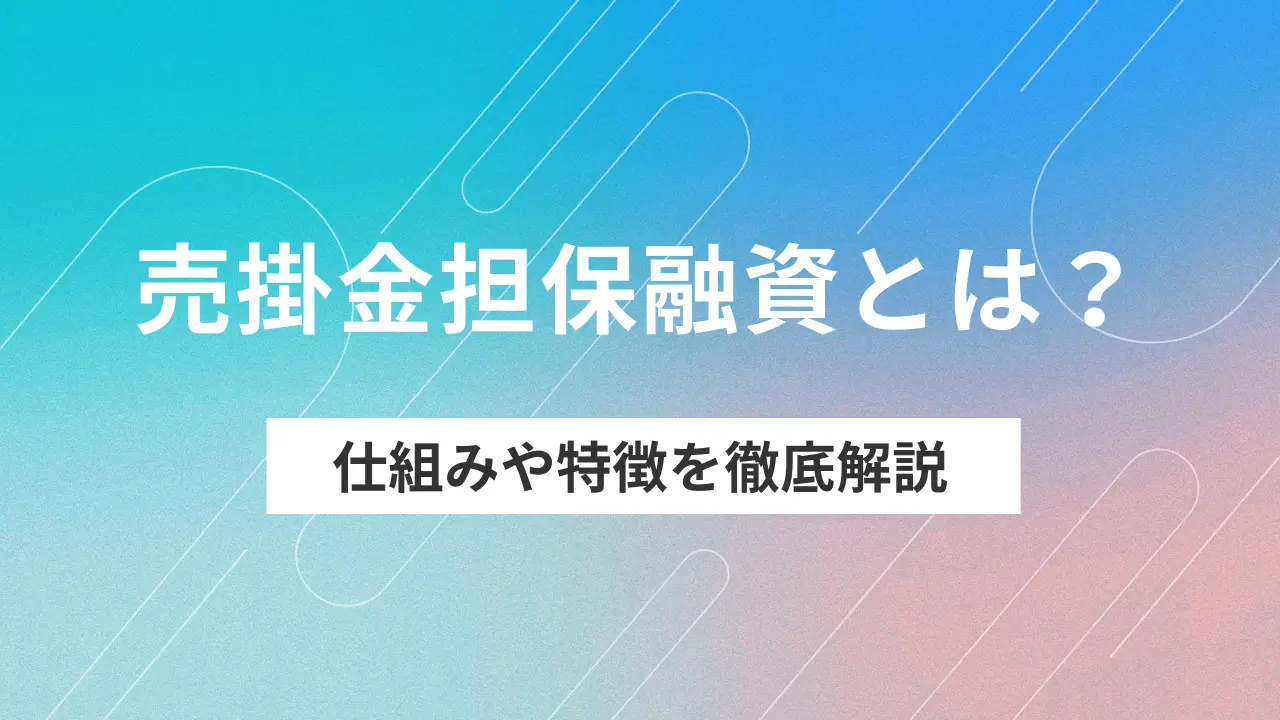



売掛金担保融資について知りたいです。
仕組みや特徴、どれぐらい資金調達できるのか詳しく知りたいです。
本記事では、こういった疑問・要望にお答えします。
なお、本記事の筆者は、2009年から現在まで中小企業の資金繰り改善コンサルタントとして活動しており、年商数百万の個人事業主から年商10億円以上の企業まで、幅広く対応してきました。
こういった経験を元に、本記事では、売掛金担保融資の情報をまとめました。
売掛金担保融資に興味をお持ちの方や、仕組みや特徴を詳しく知りたい方は、ぜひ参考にしてください。


ABL(売掛金担保融資)とは、売掛金を担保にして融資を受ける資金調達方法です。
銀行融資が難しい下記のような企業でも、売掛金を担保にすることで融資を受けれるようになります。
ABLは「Asset Based Lending(アセット・ベースド・レンディング)」の略で、日本語に訳すと流動資産担保融資となります。
流動資産担保融資とは、売掛金や商品在庫等といった流動資産を担保に融資を受ける資金調達方法です。ちなみに、商品在庫に関する融資は別記事の「在庫担保融資」をどうぞ。
商取引で発生した売掛金を担保にすることで、銀行/公的機関の融資が難しい企業でも融資を受けることができる仕組みです。
売掛金担保融資による資金調達の流れは下記のとおりです。
不動産が無い、もしくは不動産はあるけど銀行/公的機関の担保に入っていて担保価値が無い場合でも、融資を受けれる仕組みです。
担保となる売掛金の評価は主に2つの側面から評価されます。
上記の順に解説していきます。
取引先の分散度とは、取引先数の多さです。
分散度は高ければ高いほど(取引先数が多い)評価対象となり、分散度が低い(取引先数が少ない)と評価対象になりません。
例えば、月商平均2,000万円の企業の場合で、売掛評価のおおまかなイメージは下記のとおりとなります。
取引先が大手企業でも取引先が1社しかないと売上の依存度が高い(リスクが高い)と判断され、売掛はほとんど評価されません。
取引の分散度と併せて、取引の継続性も評価対象となります。
基本的に、スポットでの取引は評価対象とならず、継続的な取引のみ評価対象となります。
| 評価対象 | 評価されない |
|---|---|
| 継続的な取引 | 単発の取引(スポットでの取引) |
上記のほかにも、反対債権の有無や他金融機関による債権譲渡登記など、担保として評価対象にならない要因は色々ありますが、基本的には「取引の分散度」と「取引の継続性」が評価対象となります。
担保となる売掛金の評価額が決定したら、評価額に掛け目を乗じた額の範囲内で融資が実行されます。
例えば、月商平均が2,000万円で、売掛の評価(掛け目)が8割であれば、掛け目の上限である1600万円の融資が実行されるイメージです。
以上が売掛金担保融資の主な仕組みとなります。続いて、売掛金担保融資の特徴を解説していきます。


売掛金担保融資の特徴は下記2つです。
上記のとおり。
銀行/公的機関から融資を受ける場合、財務内容に問題があると融資を受けることは非常に難しくなりますが、売掛金担保融資は下記のような問題を抱えていても利用できます。
売掛金担保融資は取引先の信用力を重視しているため、利用者企業の財務内容に多少の問題があっても、売掛金の評価が高ければ融資を実行してくれます。
銀行/公的機関に融資を申し込む際、下記のような状態にあると不動産担保を求めらます。
しかし、売掛金担保融資は不動産担保によらない仕組みなので、継続的に取引している取引先があれば、不動産担保不要で利用できます。


売掛金担保融資の注意点は下記5つです。
上記のとおり。
個人事業主は債権譲渡登記ができないため、売掛金担保融資を利用できません。
利用者が法人であっても売掛先が個人事業主の場合、売掛の評価対象にならないので利用できません。
個人事業主が売掛を利用した資金調達を行う場合、ファクタリングが現実的な選択肢となります。
ファクタリングの詳しい解説は別記事の「ファクタリングとは?仕組みや特徴、注意点を徹底解説」をどうぞ。
売掛金担保融資をサービス提供している金融機関の多くは、利用者を年商2億円以上に設定しています。
したがって、年商2億円以下の企業は利用できない場合がほとんどです。
ビジネスローン専門会社が提供している売掛金担保融資であれば、年商2億円以下でも利用できます(ただし、利用上限額が1,000万円と低いです)。
売上の回収サイトが短いと利用できません。
例えば、売上の回収サイトが20日未満の場合、金融機関によっては担保評価にならない場合がほとんどです。
売掛金担保融資は原則、債権譲渡登記が必要になります。
ただし、取引先に債権譲渡登記を行うことを知らせることはありません。
業種によっては利用が難しい・利用不可の場合があります。
具体的な業種は下記3つです。
上記の順に解説します。
建設・建築関係は利用が難しい業種の1つで、利用NGとしている金融機関が多いです(OKのところもあります)。
売上の回収サイトが短いと利用できないのでご注意ください。
ITの受託開発は利用NGとしている金融機関がほとんどです。
理由は、開発の進捗と共に売掛金が減少するため、担保評価が難しいからです。
例えば、1,000万円のシステム開発案件の場合。
契約時に2~3割程度の着手金を受け取ることが多いですが、仮に300万円の着手金を受け取った場合、残金700万円が売掛金として発生するのですが、プログラムを納入・検証した段階で全体の3~4割の入金があったりします。
この時点で300万円を受け取った場合、売掛金として残るのは400万円になります。
このように、仕事の進捗と共に売掛金が減少する業種は、売掛金として評価できないので、利用NGとなります。
飲食・小売業(EC事業者含む)は基本的に現金商売なので、利用できません。
以上が売掛金担保融資の注意点となります。続いて最後に、売掛金担保融資のよくある質問とその答えを紹介していきます。


売掛金担保融資のよくある質問とその答えは下記のとおりです。
上記のとおり。
創業間もない企業でも、継続的な取引がある売掛先が複数あれば利用できる可能性があります。
基本的な前提として、税金や社会保険料の滞納が原因で入口の段階で断られることは少ないです。滞納の度合いにもよりますが、基本的には利用できます。
ただし、税金や社会保険料を滞納していると、融資実行にあたり滞納解消が条件になるため、融資金を全額、資金繰りに使えないのでご注意ください。
例えば、税金や社会保険料を500万円ほど滞納している状態で2,000万円の融資を申し込んだ場合、融資実行にあたり「滞納を全額解消すること」を条件に出されます。
そのため、2,000万円調達できても、実際に使える資金は1,500万円になります。
融資額(2,000万円)-滞納額(500万円)= 実際に使える資金(1,500万円)
税金や社会保険料を滞納していると実際に使える金額は減ってしまいますが、融資した資金で滞納を解消できるので、納税資金として活用している企業もあります。
リスケジュール中でも利用できます。
むしろ、リスケジュール中の企業が積極的に活用すべきだと思います。
売掛債権担保融資を扱っている金融機関の多くは譲渡禁止特約の入っている売掛債権を評価対象としません。
2020年4月に新民法が施行され、債権譲渡禁止特約が入っている契約でも債権譲渡が可能になったとはいえ、取引先と利用者企業との間では、譲渡禁止特約違反は契約違反です。
つまり、損害賠償や契約解除の対象になります。
損害賠償や契約解除の対象になれば、売掛金の担保価値はゼロです。
契約解除になれば取引先を失う訳ですから、売掛金の価値はゼロです。
ただし、全ての金融機関が一律で評価対象から外している訳ではありません。一部の金融機関では条件さえ整っていれば評価金額に加えて、融資を検討してくれるところもあります。
詳細は、申し込み時に「取引先との契約で譲渡禁止特約が入っているけど、融資可能か?」と相談してみてください。
売掛金担保融資の利用がバレるケースは下記2つです。
ちなみに、取引先に債権譲渡登記事項概要ファイルを請求されたら売掛金担保融資を利用していることはバレるとはいえ、債権譲渡登記事項概要ファイルを請求されること自体、かなりレアケースです。
ですので、実際はほとんどバレることはありません。
以上、ABL(売掛金担保融資)に仕組みや特徴、注意点を解説しました。
銀行/公的機関の融資が難しい企業でも、継続取引がある取引先が多ければ売掛金担保融資で調達できる可能性があります。リスケジュール中で新規融資が難しい企業や、財務内容に問題を抱えている企業でも利用できるので利便性は高いです。
ただし、銀行/公的機関の融資と比べて金利は高いので、安易に利用すると利益率悪化の原因となります。
また、万が一返済が遅れてしまった場合、金融機関は取引先から売掛金を回収することになるため、取引停止のリスクもあります。取引先が大手企業だと取引停止は避けられませんので、利用を視野に入れている場合、慎重に検討するようにしましょう。